1973年秋に全世界を襲った石油ショックは、わが国の産業界にも多大な影響を及ぼした。消費の低迷と原材料費や人件費の高騰で、赤字企業が続出し、どの企業も『減量経営』に追い込まれてしまったからである。
旭化成も例外ではあり得ず、収益は急速に悪化した。1976年3月期には、遂に23億円の経常赤字に陥り、その後も業績回復のメドは立たなかった。赤字に転落したのは、戦後初めてのことである
こうした事態を乗り切るため、私はやむを得ず遊休土地や所有株式の売却に踏み切った。資産の売却益は3年間で200億円にのぼったが、これらの利益がなければ配当の継続はむずかしかったのである。もちろん、人減らしもやり、この期間中に3割近い人員を削減した。
ひと口に人減らしと言うが、経営者にとってこれほど辛いものはない。しかし経営の実情をよく理解し「私が辞めることで会社が助かるのなら」と多くの人が進んで協力してくれた。私はこれらの人たちの協力に心から感謝するとともに、そのひとりひとりが辞めたあとでもなんとかやっていけるよう、きめ細かいお世話をすることを指示し、現場の管理者も私と同じ気持ちで対応してくれた。しかし、石油ショックの後遺症は、個々の企業が合理化すれば済む問題ではない。どうしても業界全体で構造改善を進める必要があった。
私は合繊不況のさ中の1977年4月、再び日本化学繊維協会の会長に就任した。そこで真っ先に設備の過剰対策に取り組もうと考えた。合繊不況の根本的な要因は、高度成長時代に増強した設備の過剰にあると判断したからである。
そこで、まず、不況カルテルを申請した。しかし、実際の設備能力と届け出の数字が違っていることを、新聞にスッパ抜かれてしまった。そのため、いったん申請を取り下げ、実際の能力と届け出能力の差を修正する作業を始めた。
ところが、この作業は思いのほか手間取った。社長会で激論を戦わせる場面もあったが、お互いに過去のことは言わず現実に即して訂正する努力を続けた。その結果、社長同士に信頼関係が生まれ、正確な数字を出し合うようになったのである。
各社の社長だけで話し合うと、独禁法とのからみで誤解される恐れがあるから、通産省の局長や課長にも立ち会ってもらった。不況カルテルだと申請から認可まで時間がかかるので困っていたら、当時の所管局長が通産大臣に話をし、総理大臣の了解を取り付けて、鉄鋼以来12年振りに勧告操短を決めてくれたのである。
これによって様相は一変した。合繊不況脱出の契機は、この勧告操短にあった。私は今でもその人に感謝している。
かくて、同年10月から通産省の行政指導による平均20%の減産が実施された。そして、半年後の1978年4月には不況カルテルに切り替えることができたのである。
構造改善の方も、特定不況産業安定臨時措置法による構造不況業種に指定されたので、最終的には設備能力の17%強を廃棄もしくは凍結した。
これらが比較的スムーズにいったのは、社長同士に信頼感が芽生え、協調ムードが出てきたからだ。その意味で、社長会の開催は大きな効果があった。
もっとも、帝人の大屋晋三(おおや しんぞう)社長(故人)が唱えられた業界再編成については、残念ながら意見の一致を見ることができなかった。
大屋構想は、合繊各社の販売部門を、帝人—ユニチカ、東レ—クラレ、三菱レイヨン—東洋紡、旭化成—鐘紡の4グループに再編しようというもの。
しかし、総論はいいとしても、各論になると実現はむずかしく、結局は三菱レイヨン—東洋紡の「ダイヤファイバーズ」(アクリル部門のみ)、旭化成—鐘紡の「日本合成繊維」の2グループしか共同販売会社はできなかった。
1978年5月に設立した日本合成繊維は、両社の出向社員が自分の会社の製品を別々に売る、俗に『形式共販』と呼ばれるものだが、それでも不十分ながらグループ化の推進には役立っている。
いろんないきさつはあったものの、役所のリードだけでなく、業界自体の自助努力で構造改善を進められたことは、有意義なことであった。やはり、操短の歴史を繰り返してきた繊維業界ならでは、という気がする。
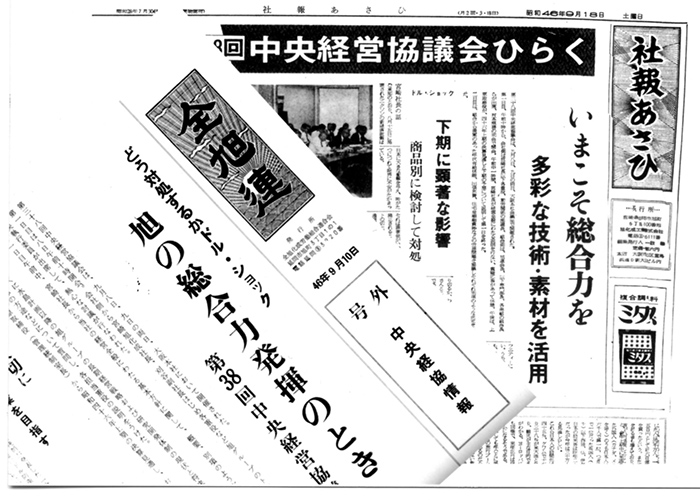 ドル・ショック対処を呼びかける社内報と組合機関紙(1971年)
ドル・ショック対処を呼びかける社内報と組合機関紙(1971年)

